退職金制度と相性抜群の“もうひとつの年金”を、わかりやすく解説
新NISAが開始して1年半。資産形成の話題をよく見かけるようになりました。
「とりあえずNISAやっておけば安心」──そんな空気があるのも事実です。
でも、老後資金をつくるという視点で見ると、実はもうひとつ、“見逃してはいけない制度”があります。
それが、iDeCo(イデコ)=個人型確定拠出年金です。
私はこれまで、労働組合の活動を通して社会保障制度の説明を行い、
FPや社労士の勉強を通じて制度の仕組みや背景を深く学んできました。
その中で強く感じたのは、
「NISAよりiDeCoを優先した方がいい人は、けっこう多い」
ということです。
この記事では、
- NISAとiDeCoの違い
- iDeCoが“第二の退職金制度”といわれる理由
- なぜ会社の退職金制度と相性がいいのか
を、できるだけシンプルに解説していきます。
1|NISAとiDeCo、何がどう違う?
正直、iDeCoはNISAより“地味”です。
ですが、制度の目的がまったく違うのです。
📊 NISAと iDeCoの特徴比較

📌 公式解説リンク
2|iDeCoは“第二の退職金制度”と考えてみる
iDeCoの本質は、**「自分で作るもうひとつの退職金制度」**です。
なぜなら、会社の退職金制度と非常に似た税制メリットがあるからです。
たとえば、毎月2万円を積み立てると──
- 年間24万円が全額所得控除
- 年収500万円なら、約5万円の節税効果
- 運用益も非課税(通常は約20%の税がかかる)
- 受け取り時にも税制優遇あり(退職金or年金として)
📌 公式出典
普通の貯金やNISAと比べて、
「税金がかかる前にお金をよけておける」
これが、iDeCoの最大の強みです。
3|退職金制度とiDeCoが相性抜群な理由
現在の企業の退職金制度、十分とは言えません。
- 終身雇用の崩壊
- 退職金の減額傾向
- 企業年金がない会社も多い
そのため、iDeCoは「退職金制度が薄い会社に勤めている人」の自衛手段になります。
そして何より重要なのが──
iDeCoを一時金として受け取る場合、退職所得控除が使えるという点。
📌 公式出典
この控除を使えば、受け取り額のうち数百万円が非課税になる可能性もあります。
(例:20年以上加入していれば、最大1,200万円まで非課税)
4|一言でまとめると…
💬 NISAは「使うための投資」
💬 iDeCoは「老後に備える仕組み」
どちらも大切な制度ですが、
「安心の土台を先に作る」
という意味では、iDeCoの優先度が高くなるケースも多いのです。
🧩 まとめ
- iDeCoは「税金がかからない退職金」のようなもの
- NISAは自由に使えるが、iDeCoは老後資金に特化している
- 退職金が不安な今、「自分で作る制度」として非常に有効
✏️ おわりに
私は組合活動の中で、社会保障の仕組みをわかりやすく伝える役割をしてきました。その経験と、FP・社労士としての学びを活かしながら、これからも「制度を、やさしく解説する」を目標に記事を届けていきます。
この記事が参考になったら、引き続き本ブログをお読みいただけると嬉しいです。
✅ 脚注・補足
本記事は2025年6月時点の法制度に基づいて執筆しています。
制度は今後変更される可能性があります。
詳細は、以下の公的情報をご確認ください。
必要であれば、サムネイルやOGP用のキャッチコピー、カテゴリ/タグの提案も可能です。希望があればお申し付けください。
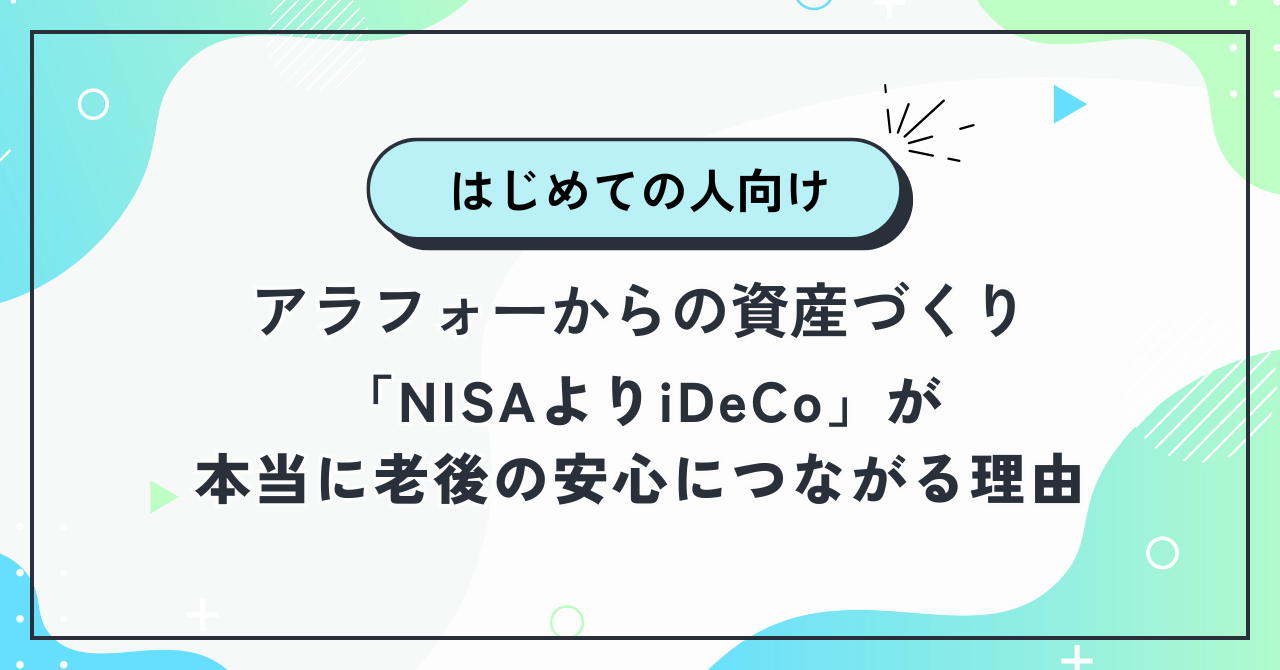
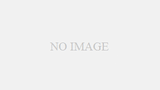

コメント